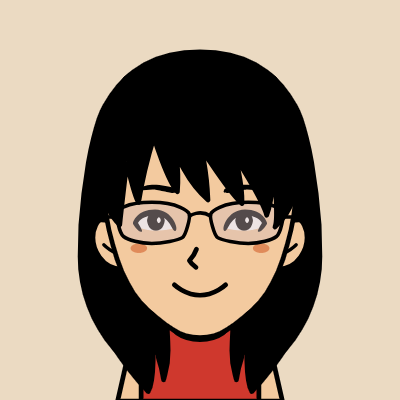小学1年生の娘を育てる中で、私は「ただのわがままなのかな?」と悩みながら過ごしてきました。特に激しい癇癪や、予定変更が苦手で大泣きする姿に戸惑い、どう接していいのかわからずイライラしてしまうことも…。そんなある日、SNSで「ASD(自閉スペクトラム症)」という言葉に出会い、特徴を調べていくうちに「うちの子も発達障害グレーなのかもしれない」と感じ始めました。
この記事では、私が娘の発達障害グレーを疑い始めたきっかけや体験、そして「特性を知ることでイライラが減り、子どもとの関わり方が変わった」ことをお伝えします。同じように「小1の壁」や子どもの育てにくさに悩んでいるママに、少しでも参考になれば嬉しいです。
娘の癇癪から始まった「違和感」
小学校に入学した頃から、娘の癇癪は一段と強くなりました。
- 思い通りにならないと1時間以上泣く
- 思い通りにいかないと物を投げる
- 暴言を吐く
もともと、保育園のころから癇癪があったが
「小1になって環境が変わったから疲れてるのかも」
と思っていました。

●●ちゃん(姉)がYouTube何回もチャンネル変える
姉との些細な喧嘩からヒートアップ。

もう、やめなさい。

カーテン引きちぎるよ
と言ったり、タブレットを投げたり
ソファーをひっくり返したり手をつけれない状態。
私自身も「どうしてこんなに育てにくいんだろう」と感じるようになったのです。
SNSで知った「ASD」という言葉
行き場のない気持ちを抱え、
SNSで癇癪で検索してみました。
そこで、癇癪の文字が目にとまり
その人の記事を見ると、
ASD(自閉スペクトラム症)」や「発達障害グレーゾーン」
という言葉を使っているのを目にしました。
ASDの特徴を調べると、
- 強いこだわりがある
- 環境や予定の変化に弱い
- 感覚過敏や癇癪が起きやすい
- 気持ちの切り替えが苦手
まさに、娘に当てることでした。
「もしかしたらうちの子もそうかもしれない」
と思った瞬間、胸のつかえが少し軽くなったのを覚えています。
「発達障害グレー」とは?
発達障害グレーとは、
医師の診断基準を満たすほどではないけれど、
日常生活で何らかの理解と配慮と工夫が必要な状態です。
- 診断基準を満たさないが特性がある
- 困りごとや生きづらさ
- 周囲の理解を得られにくい
診断があってもなくても、
毎日の生活では工夫が不可欠です。
私自身、「ただのわがまま」だと
思い込んでいたため、娘を叱りすぎてしまうことも多かったのですが、
グレーゾーンの存在を知ったことで考え方が変わりました。
特性を知ってから変わった私の対応
発達障害グレーを知ってから、
私の子どもへの関わり方は少しずつ変わりました。
- 癇癪を「わがまま」ではなく「特性」と理解する
→ 癇癪には反応せずに、気持ちがきりかわったら切り替えれたことを本人に伝える - できたことを本人に伝え成功体験をさせる
→ 一人でできたことを、できたね。と本人に伝える。お風呂入れたね。など - こだわりを尊重する
→ 洋服は気に入ったものしか着ないが、チグハグでも気にしない。
パジャマであっても本人がそれでいいなら、それでよし。 - 落ち着きなくても少々は目をつむる
→食事中立ち回ったり、お風呂から何回も出たり入ったりしても強くしからない。
強く𠮟るのではなく、優しい口調で伝える。
こうした工夫を重ねることで、ほとんど癇癪はなく、
以前よりスムーズに過ごせる時間が増えてきました。
私自身も「イライラして怒鳴る」ことが減り、
親子関係が少しずつ穏やかになってきたのを感じています。

同じように悩むママへ伝えたいこと
もし今、「子どもが育てにくい」「癇癪が激しくて毎日疲れる」
と感じているママがいたら、
まずは、特性があるのかも
という視点を持ってみてほしいです。
診断がついていなくても、
特性を理解するだけで子どもへの対応が変わり、
ママ自身の気持ちも楽になります。
「わがままな子」ではなく「そういう特性を持った子」だと
考えられるだけで、イライラが軽減されるはずです。
まとめ
小学1年生で見えてきた娘の癇癪や育てにくさをきっかけに、
私は発達障害グレーを意識するようになりました。
SNSで知識を得て「ASDの特性に似ている」と気づいたことで、
子どもへの見方が大きく変わりました。
発達障害グレーという言葉を知ることは、
子どもをラベルづけするためではなく、
「親が楽になるための知恵」だと感じています。
まだ診断には至っていませんが、私はこれからも娘の特性を理解し、
寄り添いながら育てていきたいと思います。
同じように「小1の壁」や「癇癪」で悩んでいるママへ――。
子どもの特性を知ることは、親子関係を穏やかにする第一歩です。
わがままと捉えず「その子らしさ」として向き合うことで、
きっと育児が少し楽になるはずです。