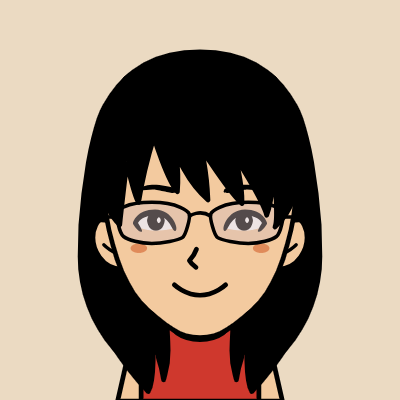小学1年の娘は、入学してから行き渋りが続いています。病院ではまだ診断がついていませんが、発達障害のグレーゾーンではないかと感じることが増えました。学習面や生活面での特性があって学校生活に遅れをとっていて、学校を苦痛に感じています。これからの学校生活をどうしていくか悩むようになりました。
そんな中、思い切って「支援学級」の見学に行ってきました。
娘のペースで学習ができ、娘の過ごしやすい環境で学校に通うことができたらいいなと思ったからです。
今回はそのときの感想や、制度の複雑さに戸惑った体験を正直に綴りたいと思います。
同じように「支援学級を検討しているけれど迷っている」という保護者の方の参考になれば幸いです。
行き渋りが続く娘——発達障害グレーを疑いはじめたきっかけ
1年生の5月ごろから、娘が「学校に行きたくない」と言うようになりました。
GW明けで行きたくないのかな思っていましたが、泣いて登校を拒否する日も増えていきました。
癇癪やこだわりの強さ、予定変更への抵抗など、SNSなどで調べるうちに、ASD(自閉スペクトラム症)グレーゾーンの特徴に似ている部分が多いと気づきました。
医師の診察を受けようと決めたものの、予約は数か月待ち。
その間も「今の環境でこのまま過ごしていいのか」という不安が募り、
カウンセラーの先生のアドバイスで支援学級の申し込みと支援学級の見学を決めました。

初めての支援学級見学——感じた「安心」と「戸惑い」
見学に行った支援学級は、少人数で先生の目が届きやく、落ち着いた雰囲気。
授業もゆっくりと進み、ひとりひとりに合わせたサポートがされていました。
「この環境なら、娘も安心して学べるかもしれない」
そう感じる一方で、気になる点もありました。
1年生と6年生が同じ教室で学んでおり、1年生の授業と6年生の授業を同時にします。
一方の授業を進めている間、他の子どもは自習をしている場面もありました。
そのため、学習の進み方に大きな差がつきやすい印象を受けました。
娘は学力的には問題がないタイプなので、「このクラスだと学力に大きな差がでるのではないか?」と少し違和感を持ちました。
支援学級には「知的」と「情緒」があることを初めて知る
見学後、先生に娘の環境的には良さそうだが学力の遅れがでるのが、心配であることを相談しました。
相談して初めて知ったのが、支援学級には大きく分けて「知的クラス」と「情緒クラス」があるということ。
私は最初、「支援学級はひとつ」と思っていたため知的クラスの支援学級で
すでに申し込みが進んでいました。実際には、知的クラスは学習面での支援が必要な子、情緒クラスは気持ちのコントロールや対人関係にサポートが必要な子が対象。
娘の場合は学力には問題がなく、気持ちの揺れや不安が強いタイプなので、本来であれば情緒クラスが合っているのかもしれません。
しかし、情緒クラスの就学相談はすでに締め切られており、教育委員会へ連絡し、事情を説明することになりました。
正直、情報が分かりにくく、親が自ら動かないと分からない現状に驚きました。
カウンセリングの先生、担任、教育委員会など、それぞれの話が少しずつ違い、親として混乱する場面も多かったです。
私としては、教育委員会の就学相談でどのクラスに在籍したほうがいいか相談したかったのに知的の支援学級の場合は就学相談の場がなく学校が認めていれば、入れるとのことで相談する機会がありませんでした。
通常学級で行けないよりは支援学級で登校できるほうがいいかと思っていたのであとは、娘次第だなと見学を進めていました。
そんな中、支援学級に知的のクラスと情緒のクラスがあると知ったので驚きを隠せませんでした。
情緒クラスの場合は、診断書が必要なのと就学相談が必要らしく、なんだそりゃ。最初から就学相談させてくれよ。と心から思いました。
非常にわかりにくく、困惑しました。
先生やカウンセリングの先生が理解できてないことを私が理解できるはずがありません。
情緒クラスの見学——“個別で手厚い支援”の一方で感じた難しさ
後日、情緒クラスの見学にも行ってみました。
授業は通常学級と同じカリキュラムで進みながら、子どもに合わせて個別でサポートをしてくれるとのこと。
先生が一人ひとりをしっかり見てくれる印象で、不安が強い子にとってはとても安心できる環境だと感じました。
ただ、先生との相性や、少人数ならではの人間関係の濃さが課題にもなると感じました。
娘の場合、怒られることを非常に怖がるので「先生と合わない時は、逆にしんどいかも」と思う場面も。
また、支援学級の先生の話では感情のコントロールができない子もいるので癇癪がおきている子の中で学習しなくてはいけない場面があることも教えてもらいました。
見学した時は、そういったことはなくむしろ、通常学級より漢字は速く進んでいて学習も穏やかにできていました。
見学を通して感じたこと
見学を通して、「支援がある=安心」ではなく、子どもの性格や発達の特性に合った環境を選ぶことが大切だと実感しました。
また、いろいろな方の話を聞くことがいいと感じました。その方の考えによって、考えが左右されるからです。
例えば、支援学級での学習の遅れの心配に関してカウンセリングの先生は「通常学級に行くことで学習が遅れる可能性もありますよね。」
に対して、先生は私の考えに同調する感じ。
支援学級の先生は「娘を見る限り知能の発達の遅れはないので非常にもったいない。通常学級でできると思います。学力に遅れがでると進路にも今後影響があるのでそこは十分に考えてください。」とアドバイスをもらいました。
どの先生方の考え方も間違っているとは思っていなくていろんな考えを、聞いたうえで娘にとって一番適した環境はどこだろうと考えるのが重要ではないかと思いました。
一人の方の話だけを聞くと、その方の言っていることが正しいと思い、答えに影響がでると思うからです。
今の選択——2年生はまず普通学級で様子を見ることに
見学を経て、私たちは2年生もまずは普通学級で様子を見るという選択をしました。
今でも行き渋りもありますが以前とは少しちがい背中を押せば行けたり笑顔で登校できる日も増えています。
学校に1日付き添っている日もありますが、徐々にいけるのではないかと感じています。
もちろん、まだこれでいいのか正解はわかりません。でも、支援学級を見学したことで、「いざという時にこういう環境もある」という安心感を持てたのは大きな収穫でした。
【まとめ】——親が情報を知ること、動くことが子どもを守る力になる
今回の支援学級見学を通して強く感じたのは、「知っているかどうか」で選択肢が大きく変わるということ。
制度や仕組みは複雑ですが、分からないことは学校任せにせず、教育委員会や専門機関に自分から問い合わせることで、子どもに合った環境が見つかる可能性があります。
そして何より、親が悩みながらも動いている姿は、子どもにとって「安心していいんだ」と感じられる支えになると思います。
焦らず、一歩ずつ。
我が子にとって“居心地のいい場所”を見つけていけたらと思っています。